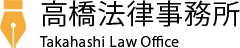弁護士髙橋正明のブログ(ハムレットのミステリー)
ハムレットのミステリー(1)
このブログでは、シェイクスピアの「ハムレット」から、
「To be or not to be, that is the question」
の台詞(セリフ)を取り上げたい。
多くの人は「生か、死か、それが問題だ」といった翻訳に親しんでいると思う。もっとも、「be」動詞が、どうして、生か、死かの意味になるのかと疑問をお持ちの方もあるかと思うが、ご心配なく、シェイクスピアの研究家である中野春夫教授は、「be」という動詞は「exist」(存在する)という意味に取れ、「exist」がこの世で存在することだとすれば、「live」と同義語となり、生か、死かの訳で問題はない、と解説されている(シェイクスピアの英語で学ぶ ここ一番の決めセリフ マガジンハウス刊)。
僕は、若い頃から、「生か、死か、それが問題だ」の訳には違和感というか、微妙な語感のずれというか、何かそういったものを感じていた。
河合祥一郎訳(角川文庫)では、「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題である」とある。その「訳者のあとがき」では、約40例の日本語訳が列挙されているが、小田島雄志訳(白水Uブックス)を除いて、殆どは、前段は、生か、死か、を扱い、後段では、それが「問題」であるとか、「疑問」であるといった意味に収斂しているようだ。何故に、たった1行の台詞には統一性がなく、多岐にわたるのか、中野春夫教授は「この台詞はシェイクスピア劇のなかでも難解中の難解として知られてきたものです。古来より数多くの研究者たちがこの神秘的な台詞に挑んできましたが、答えは百出するばかりです。この簡単な1行で私たち人間の悩みすべてを凝縮していると言っても過言ではありません」とあるのだ(前掲書)。
「To be or not to be, that is the question」
の台詞(セリフ)を取り上げたい。
多くの人は「生か、死か、それが問題だ」といった翻訳に親しんでいると思う。もっとも、「be」動詞が、どうして、生か、死かの意味になるのかと疑問をお持ちの方もあるかと思うが、ご心配なく、シェイクスピアの研究家である中野春夫教授は、「be」という動詞は「exist」(存在する)という意味に取れ、「exist」がこの世で存在することだとすれば、「live」と同義語となり、生か、死かの訳で問題はない、と解説されている(シェイクスピアの英語で学ぶ ここ一番の決めセリフ マガジンハウス刊)。
僕は、若い頃から、「生か、死か、それが問題だ」の訳には違和感というか、微妙な語感のずれというか、何かそういったものを感じていた。
河合祥一郎訳(角川文庫)では、「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題である」とある。その「訳者のあとがき」では、約40例の日本語訳が列挙されているが、小田島雄志訳(白水Uブックス)を除いて、殆どは、前段は、生か、死か、を扱い、後段では、それが「問題」であるとか、「疑問」であるといった意味に収斂しているようだ。何故に、たった1行の台詞には統一性がなく、多岐にわたるのか、中野春夫教授は「この台詞はシェイクスピア劇のなかでも難解中の難解として知られてきたものです。古来より数多くの研究者たちがこの神秘的な台詞に挑んできましたが、答えは百出するばかりです。この簡単な1行で私たち人間の悩みすべてを凝縮していると言っても過言ではありません」とあるのだ(前掲書)。
ハムレットのミステリー(2)
シェイクスピアの「ハムレット」、セルバンテスの「ドン・キホーテ」は世界文学の至宝と言われているが、この巨匠の類似点をあえて二つあげれば、一つは性格描写にすぐれた文豪であること、そして、奇しくも、二人とも1616年4月23日に亡くなっていることであろうか。
「ハムレット」は、死後の世界をあれやこれや追及したものではない。
後半のハムレットの独白(台詞)でも、
名誉が関わるとなれば、たとえ藁(わら)しべ一本のためにも、
命をかけて立ち上がることだ。
ところが、この俺はどうだ。
父を殺され、母を汚され、
理性も血潮も沸きたつ理由がありながら、
何もかも眠らせている。恥を知れ。
とあって、「復讐」と「理性」との葛藤を描いた作品だ。
もっとも、その底流には、正義感や公正、死生観などが潜在しているのである。
「ハムレット」は、死後の世界をあれやこれや追及したものではない。
後半のハムレットの独白(台詞)でも、
名誉が関わるとなれば、たとえ藁(わら)しべ一本のためにも、
命をかけて立ち上がることだ。
ところが、この俺はどうだ。
父を殺され、母を汚され、
理性も血潮も沸きたつ理由がありながら、
何もかも眠らせている。恥を知れ。
とあって、「復讐」と「理性」との葛藤を描いた作品だ。
もっとも、その底流には、正義感や公正、死生観などが潜在しているのである。
ハムレットのミステリー(3)
このブログでは、僕は、シェイクスピアは、当初の台詞は、
To take revenge or not to take、that is the question
(復讐すべきか、否か、それが問題である)
と構成していたが、これを変更して、現行の
To be or not to be, that is the question
と再構成したとの仮説をたてたのである。この難解な「台詞」を統一的に説明するには理論的な仮定が必要であった。そして、この生か、死を扱った1行の神秘的ともいえる孤高の「台詞」こそが、「ハムレット」の「核」であり、ハムレットを「ハムレット」たる所以とするものであろうと考えている。無論、このブログは、「ハムレット」の読み方の一つの切り口を提供したものに過ぎない。
だから、気軽に読んでいただきたい。もし、「ハムレット」を読んだことがない人がいても、大丈夫である、ハムレットの理解に必要な「台詞」は掲載してあるからだ。
To take revenge or not to take、that is the question
(復讐すべきか、否か、それが問題である)
と構成していたが、これを変更して、現行の
To be or not to be, that is the question
と再構成したとの仮説をたてたのである。この難解な「台詞」を統一的に説明するには理論的な仮定が必要であった。そして、この生か、死を扱った1行の神秘的ともいえる孤高の「台詞」こそが、「ハムレット」の「核」であり、ハムレットを「ハムレット」たる所以とするものであろうと考えている。無論、このブログは、「ハムレット」の読み方の一つの切り口を提供したものに過ぎない。
だから、気軽に読んでいただきたい。もし、「ハムレット」を読んだことがない人がいても、大丈夫である、ハムレットの理解に必要な「台詞」は掲載してあるからだ。
ハムレットのミステリー(4)
小田島雄志訳では、前段(To be or not to be)を「このままでいいのか、いけないのか」と解されて、「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」と訳されている。何故、このような訳になったのか、次の理由を述べておられる(「シェイクスピアの描く人間こそが、いちばん現代的だと思ったんです」―阿川佐和子のこの人に会いたい。週刊文春2012・12・20)。
東大時代、中野好夫先生の講義によって、これは「To live, or to die」(生か死かの問題)じゃない、もっと曖昧なもんや」と言われたことが契機となって「シェイクスピアは大事なセリフは曖昧に始めるんだ」と気づいた。
その曖昧さを、ハムレットは、(この台詞に続いて)
「Whether ‘tis nobler…」(どちらが立派な生き方か)と続けて、(ア)このままこころのうちに、暴虐な運命の矢弾をじっと耐えしのぶことか、(イ)それとも寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつことかと述べている(ア)、(イ)は付記)。
「To be」とは、(あ)現状のまま無為にいきることであり、「not to be」は(い)死を賭して現状を打ち破ることであって、(ハムレットは)自分の存在ではなく、自分の置かれた状況を肯定するか否定するか問うているのであるから、現状維持か、現状打破と解すべきであり、この意味で(台詞の前段は)「このままでいいのか、いけないのか」となると説明されている((あ)、(い)は付記)。
東大時代、中野好夫先生の講義によって、これは「To live, or to die」(生か死かの問題)じゃない、もっと曖昧なもんや」と言われたことが契機となって「シェイクスピアは大事なセリフは曖昧に始めるんだ」と気づいた。
その曖昧さを、ハムレットは、(この台詞に続いて)
「Whether ‘tis nobler…」(どちらが立派な生き方か)と続けて、(ア)このままこころのうちに、暴虐な運命の矢弾をじっと耐えしのぶことか、(イ)それとも寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつことかと述べている(ア)、(イ)は付記)。
「To be」とは、(あ)現状のまま無為にいきることであり、「not to be」は(い)死を賭して現状を打ち破ることであって、(ハムレットは)自分の存在ではなく、自分の置かれた状況を肯定するか否定するか問うているのであるから、現状維持か、現状打破と解すべきであり、この意味で(台詞の前段は)「このままでいいのか、いけないのか」となると説明されている((あ)、(い)は付記)。
ハムレットのミステリー(5)
一般には、小田島雄志訳はより正確な表現であると解されているようである。「生か、死か、それが問題だ」といった通常の解釈(訳)には違和感があったが、小田島雄志訳にはそれがない。しかし、だからといって、にわかに賛成できない。その理由について、以下に略説する。僕は、シェイクスピアは、当初の台詞は、
To take revenge or not to take、that is the question
(復讐すべきか、否か、それが問題である)
と構成していたとの仮説をたてている。小田島雄志訳は、表現は異なるが、この「復讐」の台詞と実質的には同じ解釈論(論旨)に基づいているようである。復讐すべきかは、(イ)(い)(現状打破)であり、復讐すべきでない(=否か)は、(ア)(あ)(現状維持)に相当するであろう((ア)から(あ)を(イ)から(い)を推論されているようである)。
To take revenge or not to take、that is the question
(復讐すべきか、否か、それが問題である)
と構成していたとの仮説をたてている。小田島雄志訳は、表現は異なるが、この「復讐」の台詞と実質的には同じ解釈論(論旨)に基づいているようである。復讐すべきかは、(イ)(い)(現状打破)であり、復讐すべきでない(=否か)は、(ア)(あ)(現状維持)に相当するであろう((ア)から(あ)を(イ)から(い)を推論されているようである)。
ハムレットのミステリー(6)
小田島雄志訳の問題点は、(イ)(い)(現状打破)の箇所であり、(い)死を賭して現状を打ち破ること(この「台詞」の後に)(イ)寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつ、などの台詞があって、(い)死を賭して現状を打ち破るとは、(イ)と相まって、「復讐」の台詞と同じく、相当に過激であって、王クロ-ディアスに対し(ハムレットの抱く)復讐の念を不用意に挑発することになろう。
実は、王クロ-デイアスは、物陰に隠れて、ハムレットの台詞(To be or not to beを含む)の一部始終を聞き及んでいた。そして、以下の感想(所感)を述べているのである。
いささか脈絡を欠いているが、
狂乱の言辞とはおもえぬ。胸になにかあるのだ、
それを憂鬱がじっと抱いてはぐくんでいるのだ、
殻を破り、雛にかえったあかつきは
危険なものになるかもしれぬ。それに先手をうって、
あれをイギリスにつかわす。
海を越え、異国におもむけば、
さまざまな珍しい風物に接することによって
胸にわだかるものも消え失せよう
(小田島雄志訳から抜粋)
実は、王クロ-デイアスは、物陰に隠れて、ハムレットの台詞(To be or not to beを含む)の一部始終を聞き及んでいた。そして、以下の感想(所感)を述べているのである。
いささか脈絡を欠いているが、
狂乱の言辞とはおもえぬ。胸になにかあるのだ、
それを憂鬱がじっと抱いてはぐくんでいるのだ、
殻を破り、雛にかえったあかつきは
危険なものになるかもしれぬ。それに先手をうって、
あれをイギリスにつかわす。
海を越え、異国におもむけば、
さまざまな珍しい風物に接することによって
胸にわだかるものも消え失せよう
(小田島雄志訳から抜粋)
ハムレットのミステリー(7)
王クロ-デイアスは、脈略(表現の筋道)に欠けるが、胸に何か一物(いちもつ)があって、将来の危険性を秘めているが、それでもなお異国で珍しい風物に接することによって、治癒するだろう、といった感触を抱いている。もし、クロ-デイアスが(自己に向けられた)ハムレットの復讐の念を嗅ぎ取っていたら、ハムレットは直ちに外国に送致され首を刎ねられたいたであろう(「ハムレット」の後半ではこの旨が描かれている)。小田島雄志訳では、週刊文春での説明によって、現状維持か現状打破か、その内容が説明されているが、相当に過激であり、クロ-デイアスの感想(所感)を逸脱し整合性を欠くことになろう。
「ハムレット」の小田島雄志訳は名訳であるが、この「台詞」に限っていえば、「ダメだし」を出さなければならない。
「ハムレット」の小田島雄志訳は名訳であるが、この「台詞」に限っていえば、「ダメだし」を出さなければならない。
ハムレットのミステリー(8)
ハムレットといえば、猪突猛進型のドンキ・ホーテとは対極にある人物として、思索・懐疑型であって、決断・実行力に乏しい性格である、といった世界的な評価が定着している。しかしながら、この評価の是非はともかく、「台詞」の解釈において、これに拘泥すると、どうしても、「後段」(that is the question)では、文理解釈上、やむを得ないことではあるが、「それが問題だ」、「それが疑問だ」といった解釈論を導いくであろう。そして、そのことによって「前段」(To be or not to be)の意味をも規制して、たとえば「曖昧なもの」の意味が採用されて、「後段」の解釈との整合性を促がす傾向があるのでないだろうか。
もっとも、一見矛盾するかも知れないが、「台詞」が「曖昧性」を帯びていたことは当然であって、曖昧でなければ、クロ-デイアスの許容範囲を逸脱して、ハムレットの命運は尽きていたであろう。では、その曖昧さとは何か。このあたりにも「台詞」の解釈の難解性があるようだ。
ハムレットが置かれた状況は非道・無慙なものであって、現状維持などあり得ない、生か、死かの極限的な状況に追い込まれていたのである。では、ハムレットに屈辱を与え、苦悩のどん底に追い込んだ状況とは何か、以下に検討したい。
もっとも、一見矛盾するかも知れないが、「台詞」が「曖昧性」を帯びていたことは当然であって、曖昧でなければ、クロ-デイアスの許容範囲を逸脱して、ハムレットの命運は尽きていたであろう。では、その曖昧さとは何か。このあたりにも「台詞」の解釈の難解性があるようだ。
ハムレットが置かれた状況は非道・無慙なものであって、現状維持などあり得ない、生か、死かの極限的な状況に追い込まれていたのである。では、ハムレットに屈辱を与え、苦悩のどん底に追い込んだ状況とは何か、以下に検討したい。
ハムレットのミステリー(9)
父のデンマーク王の亡き後、叔父クロ-デイアスが王位を承継、デンマーク王の寵愛を一身に受けていた母ガートルードは、悲しみの痛手も癒えないうちに、王クロ-デイアスと再婚する。
父上と兄弟とはいえ、
おれがヘラクレスとちがうほど
似ても似つかぬあの男と、
一月(ひとつき)もたたぬのに、
泣きはらした赤い目から空涙の跡も消えぬうちに
結婚したとは。ああ、なんというけしからぬ早さだ。
こんなにすばやく不義の床に送りこむとは
これはよくないぞ、けっしてよい結果にはならぬぞ。
ハムレットは、自らの環境の激変によって、母との確執が生じる。自死をも願っている―神が自殺を禁じていなければ―。その最中、ハムレットは、亡き父であるデンマーク王の亡霊によって、王クロ-デイアスが自分の父親を毒殺したことを知るにいたる。夜毎、城壁近くを甲冑に身を固めてデンマーク王(ハムレットの父)の亡霊が彷徨っている事実が確認する。ある夜、亡霊はハムレットを近くに呼び寄せるのだ。ハムレットは、部下のホレイシオ・マーセラスの制止を振り切って、
なにを恐れることがある、
この世の仮のいのちなら針ほどにも惜しくない
といって、 亡霊に近づく。
(以上、小田島雄志訳から抜粋)
父上と兄弟とはいえ、
おれがヘラクレスとちがうほど
似ても似つかぬあの男と、
一月(ひとつき)もたたぬのに、
泣きはらした赤い目から空涙の跡も消えぬうちに
結婚したとは。ああ、なんというけしからぬ早さだ。
こんなにすばやく不義の床に送りこむとは
これはよくないぞ、けっしてよい結果にはならぬぞ。
ハムレットは、自らの環境の激変によって、母との確執が生じる。自死をも願っている―神が自殺を禁じていなければ―。その最中、ハムレットは、亡き父であるデンマーク王の亡霊によって、王クロ-デイアスが自分の父親を毒殺したことを知るにいたる。夜毎、城壁近くを甲冑に身を固めてデンマーク王(ハムレットの父)の亡霊が彷徨っている事実が確認する。ある夜、亡霊はハムレットを近くに呼び寄せるのだ。ハムレットは、部下のホレイシオ・マーセラスの制止を振り切って、
なにを恐れることがある、
この世の仮のいのちなら針ほどにも惜しくない
といって、 亡霊に近づく。
(以上、小田島雄志訳から抜粋)
ハムレットのミステリー(10)
亡霊(デンマーク王)
これより語る話、心して聞け
聞けば、そなたは復讐せねばならぬ
我こそは、そなたが父の霊魂
しばらくは夜毎にさまようが運命
悪逆非道の殺人に復讐せよ
卑劣な殺人だ
いかなる殺人も卑劣だが
これほど、無慙(むざん)、異常、卑劣な殺人はない
ハムレット
早く、聞かせてください。
千里を走る恋心よりも早い翼をつけて、
復讐へと飛んでいきましょう。
亡霊(デンマーク王)
デンマーク王(ハムレットの父)は、
果樹園で昼寝しているところを毒蛇に
噛まれたことになっているが、
だが、知るがいい、気高い息子よ、
そなたの父をかみ殺した毒蛇は、
今、頭に王冠を戴いている。
ハムレット
わが魂の予感どおりだ。叔父が。
(以上、河合祥一郎訳からの抜粋)
これより語る話、心して聞け
聞けば、そなたは復讐せねばならぬ
我こそは、そなたが父の霊魂
しばらくは夜毎にさまようが運命
悪逆非道の殺人に復讐せよ
卑劣な殺人だ
いかなる殺人も卑劣だが
これほど、無慙(むざん)、異常、卑劣な殺人はない
ハムレット
早く、聞かせてください。
千里を走る恋心よりも早い翼をつけて、
復讐へと飛んでいきましょう。
亡霊(デンマーク王)
デンマーク王(ハムレットの父)は、
果樹園で昼寝しているところを毒蛇に
噛まれたことになっているが、
だが、知るがいい、気高い息子よ、
そなたの父をかみ殺した毒蛇は、
今、頭に王冠を戴いている。
ハムレット
わが魂の予感どおりだ。叔父が。
(以上、河合祥一郎訳からの抜粋)
ハムレットのミステリー(11)
亡霊(デンマーク王)
わしは、眠りのうちに、
そなたの叔父が、呪わしき毒薬ヘボナの小瓶を手に
忍び寄り、わが耳に、らい病のように肉を爛れさせる、
毒薬を注ぎ込んだのだ。
弟の手によって、命も、王冠も、妃も一遍に奪われたの だ。
ああ、むごい!むごい!何という非道だ!
そなたに人の情があるならば、これを許すな。
デンマーク王室の臥を、情欲と
忌まわしき近親相姦で穢させてはならぬ。しかし、
どのような事にあたろうとも、
そなたの心を穢すな。母に危害を加えてはならぬ。
ハムレット
忘れるものか。記憶の手帳から
くだらぬ記録はきれいさっぱり消してやる。
この頭の中に刻み込まれるのは、
おまえの命令のみだ。
そうだそうとも、天に誓って!
人は、微笑んで、微笑んで、
しかも悪党たりうる、と
叔父貴よ、正体みたり、だ。俺の合言葉。
よし、誓ったぞ。
(以上、河合祥一郎訳からの抜粋
わしは、眠りのうちに、
そなたの叔父が、呪わしき毒薬ヘボナの小瓶を手に
忍び寄り、わが耳に、らい病のように肉を爛れさせる、
毒薬を注ぎ込んだのだ。
弟の手によって、命も、王冠も、妃も一遍に奪われたの だ。
ああ、むごい!むごい!何という非道だ!
そなたに人の情があるならば、これを許すな。
デンマーク王室の臥を、情欲と
忌まわしき近親相姦で穢させてはならぬ。しかし、
どのような事にあたろうとも、
そなたの心を穢すな。母に危害を加えてはならぬ。
ハムレット
忘れるものか。記憶の手帳から
くだらぬ記録はきれいさっぱり消してやる。
この頭の中に刻み込まれるのは、
おまえの命令のみだ。
そうだそうとも、天に誓って!
人は、微笑んで、微笑んで、
しかも悪党たりうる、と
叔父貴よ、正体みたり、だ。俺の合言葉。
よし、誓ったぞ。
(以上、河合祥一郎訳からの抜粋
ハムレットのミステリー(12)
ハムレット・ホレイシオ・マーセラスは、デンマーク王の亡霊が語ったことは一切口外しないことを剣に誓って約束する。ハムレットは、教養や理性などは排除して復讐の念に燃えることを誓うが、(ハムレット作品は)この復讐の決意と理性(思索)との精神的葛藤を描いているのだ。自己の存在との精神的葛藤がなければ「文学」とはいえない。ハムレットは乱心・狂気を装うが、王クロ-デイアス(叔父)・王妃ガートルード・ハムレットの最愛の恋人であるオフィーリアの父である政治顧問ポローニアスは、ハムレットの発狂の原因を突き止めるべく奔走するのである。
ポローニアスは、オフィーリアに対し、
ハムレット様は、一国の王子、生まれた星が違う、
この恋許されぬ
と諭したことが効を奏して、可憐なオフィーリアは素直に受け容れ、ハムレットは、憂鬱になり、発狂して、われわれ一同の嘆きの種となっている、と具申に及ぶのである。
王妃ガートルードは、悲嘆のオフィーリアに向かって、
ハムレットの狂乱がおまえの美しさゆえ
とわかったならば、どんなにうれしいことか。
そうであればおまえのそのやさしい気立てで
あれの心ももとにもどるでしょう
と慰める。
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
ポローニアスは、オフィーリアに対し、
ハムレット様は、一国の王子、生まれた星が違う、
この恋許されぬ
と諭したことが効を奏して、可憐なオフィーリアは素直に受け容れ、ハムレットは、憂鬱になり、発狂して、われわれ一同の嘆きの種となっている、と具申に及ぶのである。
王妃ガートルードは、悲嘆のオフィーリアに向かって、
ハムレットの狂乱がおまえの美しさゆえ
とわかったならば、どんなにうれしいことか。
そうであればおまえのそのやさしい気立てで
あれの心ももとにもどるでしょう
と慰める。
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
ハムレットのミステリー(13)
王クロ-デイアスは、兄弟殺しの罪責に慄いている。ハムレットの狂気の原因に対して鋭敏に反応している。あるとき、王クロ-デイアスは、王妃ガートルードを舞台から退場させて、
実はひそかにハムレットをここによんである、
きてみると偶然に
オフィーリアに出会うというわけだ。
と述べて、ポローニアスと共に、もの陰にかくれて、ハムレットの言動を検証して、狂気の原因がオフィーリアとの失恋によるのかどうか確認する。ハムレットは、舞台に登場して、問題の
To be or not to be, that is the question
の「台詞」(セリフ)を語るのである。(この「台詞」に続いて)
「Whether‘tis nobler…」
(どちらが立派な生き方か)
と続けて、(ア)このままこころのうちに、暴虐な運命の矢弾(やだま)をじっと耐えしのぶことか、(イ)それとも寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつことか、と語り、加えて、更に、
死ぬ、眠る、それだけだ、眠ることによって、
終止符がうてる。この世から短剣のただ
一突きでのがれることができるのに。
つらい人生をうめきながら汗水流して歩むのも
ただ死後にくるものを恐れるためだ。
死後の世界は未知の国だ、
旅たったものは一人として、
もどったためしがない。
それで決心がにぶるのだ、
見も知らぬあの世の苦労に飛びこむよりは、
慣れたこの世のわずらいをがまんしようと思うの だ。
このようにもの思う心がわれわれを臆病にする
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
など縷々独白に及ぶのである(以下、(ア)(イ)を含めて、
全体の台詞を「Nobler台詞」という)。
実はひそかにハムレットをここによんである、
きてみると偶然に
オフィーリアに出会うというわけだ。
と述べて、ポローニアスと共に、もの陰にかくれて、ハムレットの言動を検証して、狂気の原因がオフィーリアとの失恋によるのかどうか確認する。ハムレットは、舞台に登場して、問題の
To be or not to be, that is the question
の「台詞」(セリフ)を語るのである。(この「台詞」に続いて)
「Whether‘tis nobler…」
(どちらが立派な生き方か)
と続けて、(ア)このままこころのうちに、暴虐な運命の矢弾(やだま)をじっと耐えしのぶことか、(イ)それとも寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつことか、と語り、加えて、更に、
死ぬ、眠る、それだけだ、眠ることによって、
終止符がうてる。この世から短剣のただ
一突きでのがれることができるのに。
つらい人生をうめきながら汗水流して歩むのも
ただ死後にくるものを恐れるためだ。
死後の世界は未知の国だ、
旅たったものは一人として、
もどったためしがない。
それで決心がにぶるのだ、
見も知らぬあの世の苦労に飛びこむよりは、
慣れたこの世のわずらいをがまんしようと思うの だ。
このようにもの思う心がわれわれを臆病にする
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
など縷々独白に及ぶのである(以下、(ア)(イ)を含めて、
全体の台詞を「Nobler台詞」という)。
ハムレットのミステリー(14)
ふと、オフィーリアの存在に気付いて、ハムレットは、
尼寺に行くがいい、
罪深い子の母となったところで、なんになる。
父上はどこにいる。しっかり閉じ込めておくのだな。
外に出てばかなまねをしなうように。
もしおまえが結婚するというなら、持参金がわりに
呪いのことばをくれてやる。
どうしても結婚せねばならぬというなら、
阿呆と結婚するがいい。
行くのだ、尼寺へ
と狂言を繰り返す。一方、オフィーリアは、ハムレットに対して、
あれほど気高いお心が、このように無慙に!
あのかたの誓のことばの甘い蜜を吸ったこの耳で
ひび割れた鐘のような狂ったひびきを
聞かねばならぬとは。
ああ、なんて悲しい、
昔を見た目でいまのありさまを見る
この身が恨めしい!
などとしきりに詰問する。因みに、ハムレットは、もの陰に隠れていることを知っていたという説がある。興味深い意見ではあるが、僕は採用しない。
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
尼寺に行くがいい、
罪深い子の母となったところで、なんになる。
父上はどこにいる。しっかり閉じ込めておくのだな。
外に出てばかなまねをしなうように。
もしおまえが結婚するというなら、持参金がわりに
呪いのことばをくれてやる。
どうしても結婚せねばならぬというなら、
阿呆と結婚するがいい。
行くのだ、尼寺へ
と狂言を繰り返す。一方、オフィーリアは、ハムレットに対して、
あれほど気高いお心が、このように無慙に!
あのかたの誓のことばの甘い蜜を吸ったこの耳で
ひび割れた鐘のような狂ったひびきを
聞かねばならぬとは。
ああ、なんて悲しい、
昔を見た目でいまのありさまを見る
この身が恨めしい!
などとしきりに詰問する。因みに、ハムレットは、もの陰に隠れていることを知っていたという説がある。興味深い意見ではあるが、僕は採用しない。
(以上、小田島雄志訳からの抜粋)
ハムレットのミステリー(15)
ハムレットとオフィーリアは退場して、王クロ-デイアスとポローニアスが、もの陰から登場して、王による検証の結果を披露する。今回は、福田恒存訳を紹介したい。
恋!いや、そうとも思えぬ。
いささか脈絡を欠いているが、言葉の節々、
どうして狂人などであるものか―
腹に何かある。
あいつはそれを鬱々(うつうつ)として
はぐくんでいる。孵(かえ)ったら、
取り返しのつかぬことにもなろう。
何とか先手を打たねばならぬ、早速だが、
こうしよう。すぐさま、
あれをイギリスへ遣ってくれ。
海を渡って異国の風物に接すれば、
胸中のわだかまりも消えてなくなろう。
(福田恒存訳からの抜粋)
ポローニアスの感想では、狂気の原因は(オフィーリアとの関係で)「やはり片思いがもとと信じて疑いませぬ」とあって、「いささか脈絡を欠いているが、腹に危険な一物をもっている」といったの王の鋭い洞察力にははるかに及ばない。
逆説的であるが、この王の所見によって、ハムレットの「台詞」は規制されているのである。
恋!いや、そうとも思えぬ。
いささか脈絡を欠いているが、言葉の節々、
どうして狂人などであるものか―
腹に何かある。
あいつはそれを鬱々(うつうつ)として
はぐくんでいる。孵(かえ)ったら、
取り返しのつかぬことにもなろう。
何とか先手を打たねばならぬ、早速だが、
こうしよう。すぐさま、
あれをイギリスへ遣ってくれ。
海を渡って異国の風物に接すれば、
胸中のわだかまりも消えてなくなろう。
(福田恒存訳からの抜粋)
ポローニアスの感想では、狂気の原因は(オフィーリアとの関係で)「やはり片思いがもとと信じて疑いませぬ」とあって、「いささか脈絡を欠いているが、腹に危険な一物をもっている」といったの王の鋭い洞察力にははるかに及ばない。
逆説的であるが、この王の所見によって、ハムレットの「台詞」は規制されているのである。
ハムレットのミステリー(16)
河合祥一郎訳(角川文庫)の「訳者のあとがき」では、第3幕第1場では、約40例の日本語訳が列挙されている。その中で、
やる、やらぬ、それが問題だ
(小津次郎 (「世界文学全集 十」)筑摩書房)
といった訳がある。しかし、これは、余りに、直截的な表現であり、ハムレットの台詞の一部始終を聞き及んでいた王の許容範囲を逸脱する。
とはいえ、この訳は、「復讐」と「理性」との葛藤の本能的な感情の表明であり、この作品の一貫したテーマでもあって、これを否定する理由はない。
そこで、僕は、仮説として、当初、シェイクスピアは、この「台詞」の前段は、
To take revenge or not to take、that is the question
(やる、やらぬ、それが問題だ)
復讐すべきか、否か、それが問題である
といった構成を取っていたと考えている(以下(A)台詞という)。この場合、「台詞」の不自然さはなく、これに続く長文の「Whether‘tis nobler…」(特に、(ア)(イ))の台詞とも符合する。
しかしながら、(A)「台詞」では、ハムレットの「復讐」の意思を直截的に表現したものである点から、かえって、そのことによって、第3幕第1場では、表現の適格性を欠くのである。以下、2点ほど、整合性の観点から、その理由を述べる。
やる、やらぬ、それが問題だ
(小津次郎 (「世界文学全集 十」)筑摩書房)
といった訳がある。しかし、これは、余りに、直截的な表現であり、ハムレットの台詞の一部始終を聞き及んでいた王の許容範囲を逸脱する。
とはいえ、この訳は、「復讐」と「理性」との葛藤の本能的な感情の表明であり、この作品の一貫したテーマでもあって、これを否定する理由はない。
そこで、僕は、仮説として、当初、シェイクスピアは、この「台詞」の前段は、
To take revenge or not to take、that is the question
(やる、やらぬ、それが問題だ)
復讐すべきか、否か、それが問題である
といった構成を取っていたと考えている(以下(A)台詞という)。この場合、「台詞」の不自然さはなく、これに続く長文の「Whether‘tis nobler…」(特に、(ア)(イ))の台詞とも符合する。
しかしながら、(A)「台詞」では、ハムレットの「復讐」の意思を直截的に表現したものである点から、かえって、そのことによって、第3幕第1場では、表現の適格性を欠くのである。以下、2点ほど、整合性の観点から、その理由を述べる。
ハムレットのミステリー(17)
次のハムレットの台詞は、父親の亡霊に一抹の疑問を投げかけ、もっと確かな証拠の必要性を訴えた台詞である(第3幕第2場)。
いつかの亡霊は悪魔のしわざかもしれぬ。
悪魔は自由自在に、かならず人の好む姿を借りて
現れるという。
あるいはこちらの気のめいっているのに
つけこんで、おれを滅ぼそうという腹かもしれな い。
こういうときは、とかく亡霊に乗ぜられやすいも のだ。
もっと確かな証拠がほしい、
それには芝居こそもってこいだ。
きっとあいつの本性を抉りだして見せるぞ。
(福田恒存訳から抜粋)
(A)台詞では、デンマーク王の亡霊によって、復讐の決意の有無を披瀝している。しかしながら、(A)台詞では客観的な証拠に欠けるのである。ハムレットは、ドイツのプロテスタント系の大学に留学したほどのインテリであり、亡霊の言葉には全面的な信頼を寄せてはいるが、一抹の疑問を抱いていた。
NHKテレビテキスト シェイクスピア・ハムレット 河合祥一郎著によると、「カトリック」は亡霊の存在を認めるが、ハムレットが通っていたウイッテンバーグ大学は、マルチイン・ルターが教えていたプロテスタントの総本山であり、死者の亡霊は認めないとある(P30 、37)。
ハムレットにとって、諸般の事情があるとはいえ、亡霊だけによって、復讐の決意(To take revenge or not to take)を披瀝することは、客観的な証拠に欠け、軽佻浮薄の謗りを免れず、近代的な自我に目覚めているハムレットの理性・教養がゆるさない。加えて、詩情性豊かな作品の香りを失うであろう。
加えて、当時、芝居こそが真実を映し出す「鏡」であったのであるから(前掲、NHKテレビテキスト)、王クロ-デイアスの面前において、父の毒殺された情況を再現する「芝居」(劇中劇)を打って、どんな反応が返ってくるか、亡霊の信憑性を確認する必要があったのである。よって、(A)台詞は、第3幕第1場では、適切性を欠くのである。
いつかの亡霊は悪魔のしわざかもしれぬ。
悪魔は自由自在に、かならず人の好む姿を借りて
現れるという。
あるいはこちらの気のめいっているのに
つけこんで、おれを滅ぼそうという腹かもしれな い。
こういうときは、とかく亡霊に乗ぜられやすいも のだ。
もっと確かな証拠がほしい、
それには芝居こそもってこいだ。
きっとあいつの本性を抉りだして見せるぞ。
(福田恒存訳から抜粋)
(A)台詞では、デンマーク王の亡霊によって、復讐の決意の有無を披瀝している。しかしながら、(A)台詞では客観的な証拠に欠けるのである。ハムレットは、ドイツのプロテスタント系の大学に留学したほどのインテリであり、亡霊の言葉には全面的な信頼を寄せてはいるが、一抹の疑問を抱いていた。
NHKテレビテキスト シェイクスピア・ハムレット 河合祥一郎著によると、「カトリック」は亡霊の存在を認めるが、ハムレットが通っていたウイッテンバーグ大学は、マルチイン・ルターが教えていたプロテスタントの総本山であり、死者の亡霊は認めないとある(P30 、37)。
ハムレットにとって、諸般の事情があるとはいえ、亡霊だけによって、復讐の決意(To take revenge or not to take)を披瀝することは、客観的な証拠に欠け、軽佻浮薄の謗りを免れず、近代的な自我に目覚めているハムレットの理性・教養がゆるさない。加えて、詩情性豊かな作品の香りを失うであろう。
加えて、当時、芝居こそが真実を映し出す「鏡」であったのであるから(前掲、NHKテレビテキスト)、王クロ-デイアスの面前において、父の毒殺された情況を再現する「芝居」(劇中劇)を打って、どんな反応が返ってくるか、亡霊の信憑性を確認する必要があったのである。よって、(A)台詞は、第3幕第1場では、適切性を欠くのである。
ハムレットのミステリー(18)
次に、再三述べたが、物陰に隠れて観察している王クロ-デイアスの所見によって、文脈上、ハムレットの「台詞」は規制される。「いささか脈絡を欠いているが、腹に危険な一物をもっている」との王の観察所見と(A)台詞との間には、論理的矛盾があって、整合性を欠くのである。(A)台詞では、王に対して(ハムレットの抱く)復讐の念を不用意に挑発して、ハムレットの命運は尽きてしまう(ハムレットの「作品」は成立しない)。
以上、文章の構成上の観点から、第3幕第1場において、シェイクスピアは、作品の基本的テーマである(A)「台詞」の「復讐」とは不可分の関係にあって、ハムレット自身の存在の問題である「To be or not to be」も文言を採用し、現在の「台詞」である、To be or not to be, that is the questionの構成に切り替えたと考えている(以下、(B)台詞という)。
以上、文章の構成上の観点から、第3幕第1場において、シェイクスピアは、作品の基本的テーマである(A)「台詞」の「復讐」とは不可分の関係にあって、ハムレット自身の存在の問題である「To be or not to be」も文言を採用し、現在の「台詞」である、To be or not to be, that is the questionの構成に切り替えたと考えている(以下、(B)台詞という)。
ハムレットのミステリー(19)
執行草舟氏の「友よ」(講談社版)において、シェイクスピアの作品である「ジュリアス・シーザー」を扱った論考があって、詩人シェイクスピアの偉大さ、世評から受ける誤解の原因、シェイクスピア作品の解釈論について論究されている。以下、要点を摘記しておきたい。
①私の知る限り、偉大な詩の魂で劇作品を支えている劇作家は、シェイクスピアしかいない。これを現代流の劇作家と同一に捉えているところにすべての誤解の原因がある。シェイクスピアはあくまでも詩人なのだ。純粋に詩人として捉えなければ、その作品の偉大さはわからない。劇作と思っているから、現代の日本の翻訳ものも、その偉大さを伝えることはできない。
②(作品を理解するには)配役は、基本的に一人の人間の心の状態を、数人の人物に振り分けているだけなのだと見ると、非常によくできている詩だとわかる。シェイクスピアの作品の登場人物は、すべて一人なのだと極論してもよい。一人の人間がもつ、心の重層構造が織りなすあらゆる面を数人の配役に割り当てていると思うと、一貫した詩の存在を認識できる。配役にあまりこだわらず、劇中の子どもも女も老人も、すべて一人の人物、つまり主人公の言葉で再構築してみると詩劇の意味がわかる。
③「ジュリアス・シーザー」の台詞は、シーザーの言葉、キャシアスの言葉、ブルータスの言葉だが、これらの言葉はすべてシーザーの言葉と解するべきなのだ、とある。
①私の知る限り、偉大な詩の魂で劇作品を支えている劇作家は、シェイクスピアしかいない。これを現代流の劇作家と同一に捉えているところにすべての誤解の原因がある。シェイクスピアはあくまでも詩人なのだ。純粋に詩人として捉えなければ、その作品の偉大さはわからない。劇作と思っているから、現代の日本の翻訳ものも、その偉大さを伝えることはできない。
②(作品を理解するには)配役は、基本的に一人の人間の心の状態を、数人の人物に振り分けているだけなのだと見ると、非常によくできている詩だとわかる。シェイクスピアの作品の登場人物は、すべて一人なのだと極論してもよい。一人の人間がもつ、心の重層構造が織りなすあらゆる面を数人の配役に割り当てていると思うと、一貫した詩の存在を認識できる。配役にあまりこだわらず、劇中の子どもも女も老人も、すべて一人の人物、つまり主人公の言葉で再構築してみると詩劇の意味がわかる。
③「ジュリアス・シーザー」の台詞は、シーザーの言葉、キャシアスの言葉、ブルータスの言葉だが、これらの言葉はすべてシーザーの言葉と解するべきなのだ、とある。
ハムレットのミステリー(20)
人間は、神聖と冒涜,天使と悪魔、善と悪、愛と憎しみ・嫉妬、勇気と恐怖、寛大と偏狭など相対立する性質を具有する。「ハムレット」の作品では、主役であるハムレットの重層構造が織りなすあらゆる面の心理状態が王クロ-デイアス、母ガートルード、宰相ポロ-ニアス、恋人オフィーリアなどの登場人物に投影され、これらの登場人物の台詞はハムレットの言葉で再構築して解釈することにより、この詩劇の意味がわかるというのである。もっとも、シェイクスピアは、宇宙空間の言霊を鷲づかみにして、精妙に無造作に詩的な表現に還元して表現しているので、我々の理解しがたい点や矛盾点も含んでいるのも事実である。しかし、おしなべて、執行説は納得のいく正論である。
例えば、(B)台詞の独白の際、ハムレットは、王クロ-デイアスはもの陰に隠れて聞いていたという説があるが、前記の通り、僕は採用しない(NHKテレビテキストも同旨)。その際の王の台詞に「いささか脈絡を欠いているが、腹に危険な一物をもっている」とあるが(B)「台詞」では、ハムレット自身の「生か、死か」の問題にすり替わっているのであるから、(王は)自己に対する復讐の意思表示とは必ずしも受け取れない。
ハムレット自身の「生か、死か」の問題であるから、「Whether‘tis nobler…」(いずれが高貴な生きざまか)に続く冒頭部分の台詞(この部分は、復讐を意図した(A)台詞とは整合性がある)との間には、必ずしも、牽連性(けんれんせい=つながっていること)があるとも言えず、(王の観察では)文脈において「脈絡」を欠いていると解している。
しかしながら、少なくとも、「Whether‘tis nobler…」(いずれが高貴な生きざまか)に続く冒頭部分の台詞に着目する限り、王の所感では、ハムレットは腹には何か一物があって、いずれは取り返しのつかない危険性を秘めていると考察する。
このように王クロ-デイアスの台詞は、ハムレットの心理状態を如実に投影されたしたものと解することによって、相互に矛盾がなく、精緻な心理描写の展開が看取できるのである。
例えば、(B)台詞の独白の際、ハムレットは、王クロ-デイアスはもの陰に隠れて聞いていたという説があるが、前記の通り、僕は採用しない(NHKテレビテキストも同旨)。その際の王の台詞に「いささか脈絡を欠いているが、腹に危険な一物をもっている」とあるが(B)「台詞」では、ハムレット自身の「生か、死か」の問題にすり替わっているのであるから、(王は)自己に対する復讐の意思表示とは必ずしも受け取れない。
ハムレット自身の「生か、死か」の問題であるから、「Whether‘tis nobler…」(いずれが高貴な生きざまか)に続く冒頭部分の台詞(この部分は、復讐を意図した(A)台詞とは整合性がある)との間には、必ずしも、牽連性(けんれんせい=つながっていること)があるとも言えず、(王の観察では)文脈において「脈絡」を欠いていると解している。
しかしながら、少なくとも、「Whether‘tis nobler…」(いずれが高貴な生きざまか)に続く冒頭部分の台詞に着目する限り、王の所感では、ハムレットは腹には何か一物があって、いずれは取り返しのつかない危険性を秘めていると考察する。
このように王クロ-デイアスの台詞は、ハムレットの心理状態を如実に投影されたしたものと解することによって、相互に矛盾がなく、精緻な心理描写の展開が看取できるのである。